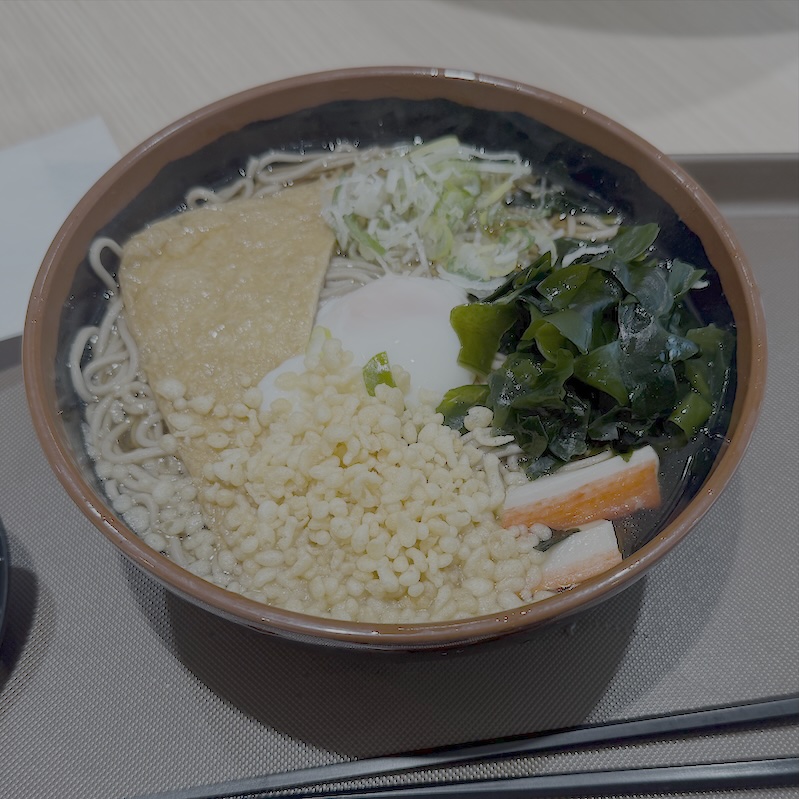今年の振り返り
気づけば今年もあと残り数時間となって、多少なりとも1年の振り返りをやっておこうと思ったので書いておきます。 今年はヨーロッパ各国を観光したり、帰省ついでに佐渡島に遊びに行ったり、 真夏の大阪・関西万博に行ったりと、数ヶ月おきに旅行に出かけていました。 ヨーロッパ旅行に備えてミラーレスカメラを買って、 友人の結婚式に参列した時もプロカメラマンに並んで写真を撮っていました。 最近は OSMO Pocket 3 も手に入れたので、撮影機材が特に充実した年だったと思います。 とはいえ、カメラは機材だけあればいいものではなく、撮影技術が重要なのはもちろんのこと、 何よりいい被写体に出会えるかが一番重要だと思います。 旅行しかり、写真を撮りたくなるようなイベントを人生に増やしたいものです。 数ヶ月前にはホットクックを買いました。 食材を切って入れてスイッチを押せば料理になっているので、 火加減を見なくてよいのが何よりも助かっています。 出社頻度が相当増えた影響で自宅にいる時間は減りましたが、 ホットクックで料理のハードルが下がって、自炊の頻度も増えたと思います。 仕事に関してはとにかく AI 一色だったように思います。 私は正直に言うと少し前まで生成 AI ブームに結構懐疑的だったのですが、 自分でも使いながら色々な人の話を聞いて、今年は自分の考え方を変えました。 LLM で AGI が実現できるかといった深遠なテーマは残っていますが、 今ある LLM で技術的に可能な領域だけでも未開拓な応用領域が多いと感じるからです。 現状の LLM だけでも日々の業務が効率化されるのは間違いなく、 これから知的労働の多くが AI に置き換えられるフェーズに入るだろうと思います。 「AI に置き換わらない仕事は何か」という議論がよくありますが、 一つの考えとして「AI に仕事を代行させる仕組みを作る仕事」はしばらく残るのではないかと思っています。 10 月に受験したプロジェクトマネージャー試験は無事合格していました。 論文試験で来年からタイピングできるようになるので、今年が最後の手書き試験でした。 仕事でもプライベートでも手書きで紙に書くことがほぼないので、 簡単な漢字でも空で書けなくなっていることに最近気づきました。 もちろん脳が扱える情報の量には限界があるでしょうし、 この時代に漢字をすらすら書けることにどのぐらい意味があるのか分かりませんが、 何の能力でも定期的に鍛えないと衰えることを如実に感じました。 まずは今年も一年健康で過ごせたのでよかったと思います。 今年の抱負で不動産を買うことにしていたのは達成できなかったので、 これは来年に持ち越しということにします。 それではよいお年を。